使ってみよう!ひきだすにほんご 〜実践共有のコーナー〜
Let's Use ひきだすにほんご! ~Examples of use~
#010
インド/オンラインコースでの実践例
他の実践例を見る
ストラテジーで日本語ブラッシュアップ!
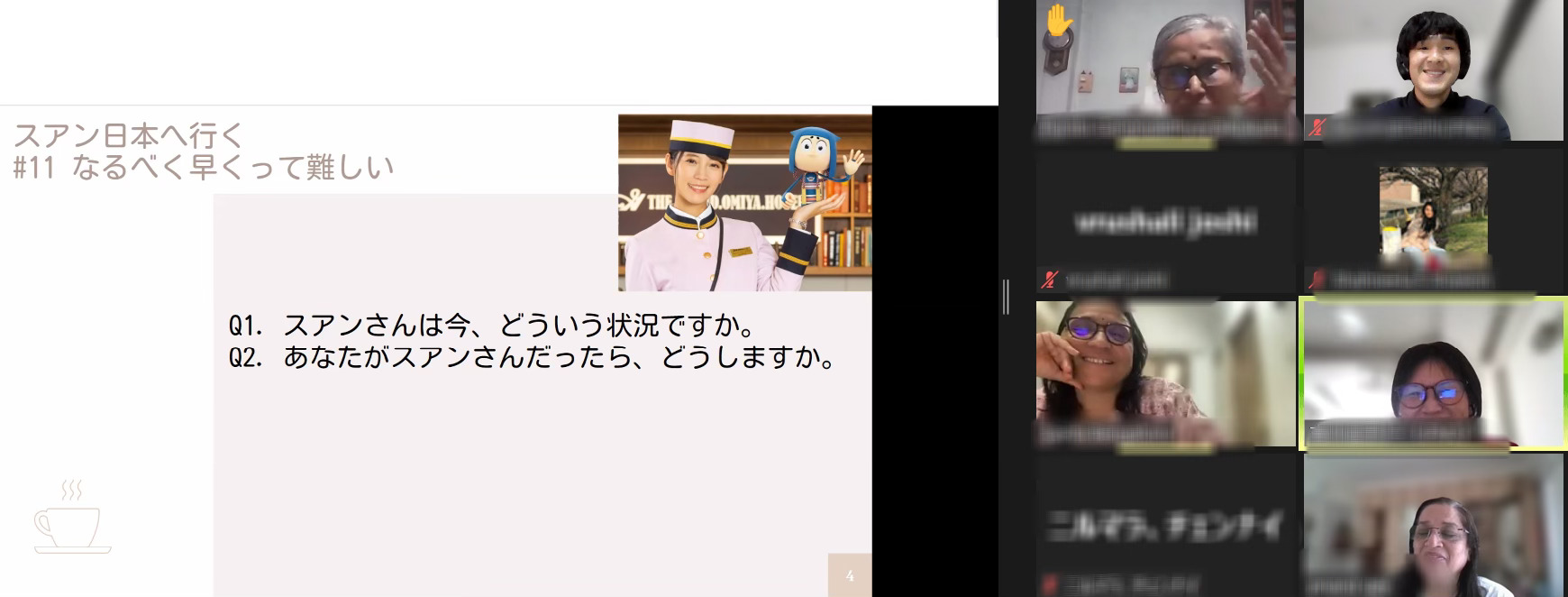
国際交流基金ニューデリー日本文化センターでは、「ひきだすにほんご」を使って、日本語教師を対象とした中級ブラッシュアップコースをオンラインで実施しました。「スアン日本へ行く!」と「気持ちが伝わるオノマトペ」6回分を1つのコースとし、先生たちが気軽に参加しやすいように、1回1時間で設定しました。このコースはこれまで同じ内容で2回(Part1、Part2)行いましたが、Part1はインドの先生たちを対象に、Part2は南アジアの先生たちに対象を広げて実施しました。Part2のコースには、インド、スリランカ、バングラデシュから21名の先生たちが参加してくれました。
こんなふうに使いました!
コースでは2つのコーナーの第7回~第12回を使いました。
| スアン日本へ行く! | 気持ちが伝わるオノマトペ | |
|---|---|---|
| 第1回 | 『今考えている』ということを相手に伝える | ごろごろ |
| 第2回 | 相手に確認しながら話す | ぴったり |
| 第3回 | 効果的にあいづちを打つ | ぼーっとする |
| 第4回 | 短くシンプルに言い換える | へとへと |
| 第5回 | 具体的な時間を確認する | すぱっと |
| 第6回 | 会話を終わらせたいというサインを出す | じーんとする |
授業の流れ
①「スアン日本へ行く!」(50分)
| 1. | ドラマ前半を視聴(スアンが課題に直面し、やんすが登場するところまで)し、簡単に内容を確認する。 |
| 2. | ブレイクアウトルームで、「スアンが困っていること」、「自分がスアンならどうするか」を話し合う。 |
| 3. | メインルームで意見を共有する。 |
| 4. | ドラマの後半を視聴(「本日のストラテジー」の前まで)し、スアンが使ったストラテジーを確認する。 |
| 5. | ブレイクアウトルームで、「どんな場面で使うストラテジーか」、「どんな表現を使うか」、「ストラテジーの効果や注意点」などを話し合う。 |
| 6. | メインルームで意見を共有する。 |
| 7. | 「本日のストラテジー(やんすの解説)」を見て、確認する。 |
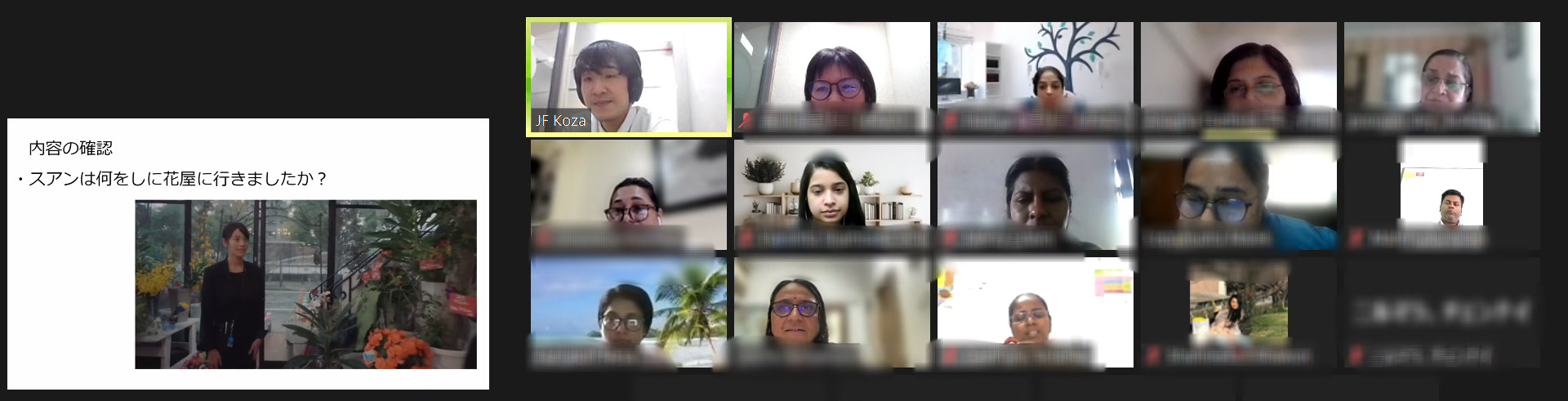
②「気持ちが伝わるオノマトペ」(10分)
| 1. | 動画の最初のイラストを見せて、オノマトペの意味を推測してもらう。 |
| 2. | 動画を視聴する。 |
| 3. | 動画に出てきた場面のイラストを見せて、どんな場面でオノマトペが使われていたかを確認する。 |
| 4. | オノマトペを使った文を作り、チャットに書いてもらい、使い方を確認する。 |
③ 最後にCan-doチェックシートにストラテジーについての理解度、自分で作ったオノマトペの文を記入してもらう。
ここをひと工夫!
オノマトペの例文づくり活動のように、成果物をみんなで共有するときには、ちょっとした工夫をするとうまくいきます。今回は、チャットを使って共有をしましたが、そのとき作った例文をすぐに送らず、「では、送ってください」という合図とともに一斉に送ってもらうようにしました。こうすることで、考えている途中でほかの人の例文が見えてしまって考えるモチベーションが下がったりするのを避けられ、それぞれがじっくり考えることができました。
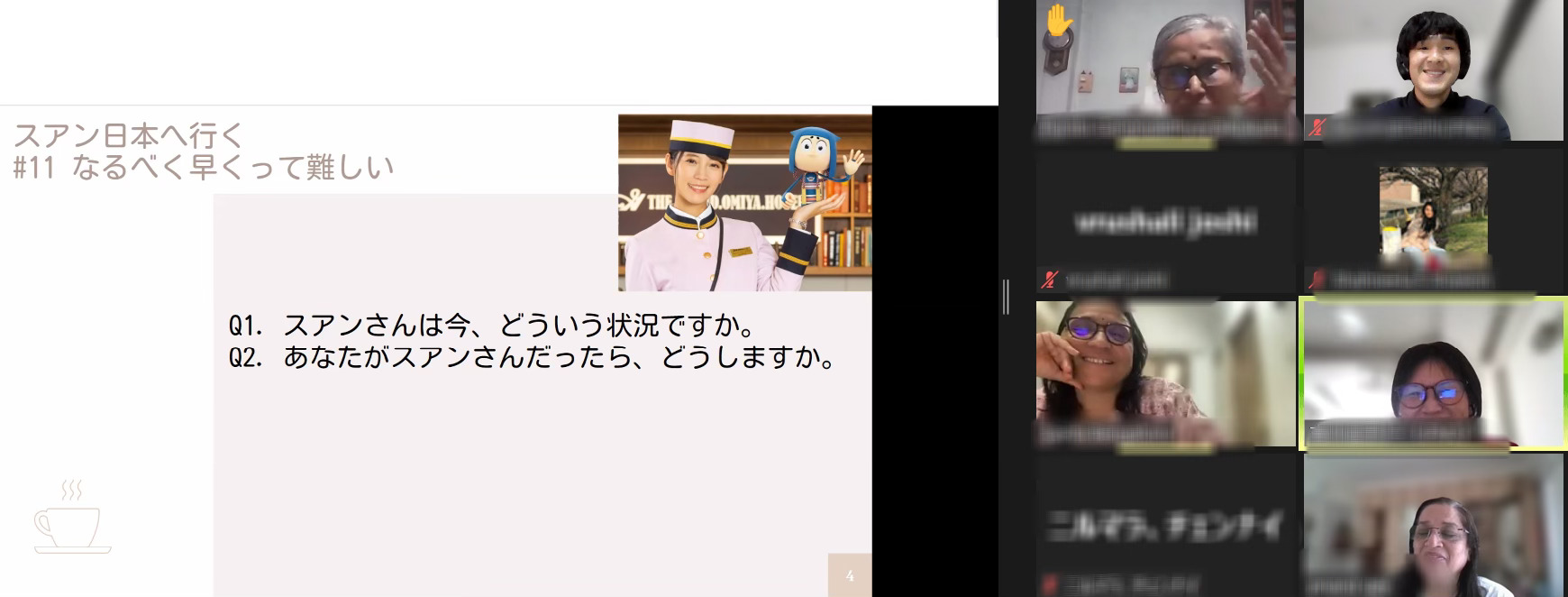
先生たちの反応
「スアン日本へ行く!」のドラマを視聴しているとき、先生たちが笑っている様子や、「なるほど」とうなずいている様子からドラマを楽しんでいることが伝わってきました。ブレイクアウトルームではもちろん、メインルームでも積極的に挙手をし、意見を共有してくれる先生が多く、授業時間をオーバーしてしまうことも多かったです。先生たちの間で特に印象に残ったストラテジーは「効果的にあいづちを打つ」だったようです。文化によってあいづちの習慣は違うので、日本語のコミュニケーションの中でのあいづちの仕方やバリエーションを知ることができたからだと思います。ブレイクアウトで話し合っているときに、早速あいづちを打ちながら話を聞くことを心がけていた先生たちもいました。
「気持ちが伝わるオノマトペ」はシンプルな状況設定で理解しやすかったようです。自分で作った文をチャットで共有してもらい、確認しているとき、「ああ、そのシチュエーション、わかる!」と反応する先生も多くいました。
アンケートには、「日本語をたくさん話す機会があってよかった!」とか、「グループで話しているときも、習ったストラテジーが使えます」などの声があり、このコースが日本語のブラッシュアップの機会としての役目を果たせたことがわかりました。また、「続きのコースをやってほしい」というリクエストがあるなど、満足度が高いコースになったと思います。

(吉川景子・澤木翔・ハディヤ・シャミム/
国際交流基金ニューデリー日本文化センター)

Sorry, this page is only available in Japanese.
このページは日本語のみでご覧いただけます





